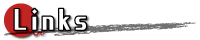TOUR Vol.8「冒険者たち」ツアーパンフから

「本物」が渇望されているこの時代が必要とする
アーティスト鈴木彩子の飾りのない素性に迫る。
1990年のデビュー以来5枚のオリジナルアルバム、そして過去7回の全国ツアーにおいて、多くの楽曲を発表し、数限りない会場でのステージを経験してきた鈴木彩子の貫き通されているスタンス。それは「ほんとのこと」しか唄わない、あるいは「ほんとのこと」しか唄いたくないという1点に全てが集約されていると言い切ってしまいたい。
なぜ彼女はその1点にこだわり続ける唄うたいなのであろうか。そのヒントは彼女の生い立ちにある。彼女の生い立ちをたどっていくと、「ほんとのこと」しか唄えないという類稀なアーティストとしての、それにふさわしい資質といったものが、確かに存在しているのだ。22歳にして、これだけさまざまな人生経験を経ているからこそ、アルバムやライブで圧倒的な説得力とリアリティが生まれ、多くの人に共感と感動と感銘を与え続けているのである。
1972年3月29日、宮城県の仙台市に隣接した岩沼市で、この世に生を受けた鈴木彩子。いじめられっ子で、体の弱かった小学生時代、彼女は水泳を始める。毎日毎日特訓の日々が続いて、本人はスイミングスクールでの練習がいやでいやでしかたなかったらしいが、めきめきと上達し、最終的には水泳で東北大会3位まで駆けのぼるという輝かしい記録を達成する。
ただ、練習が嫌いであることは変わらず「とにかく逃げ出したくてしかたのなかった」彼女は、お母さんとお姉さんがやっていたからという単純な理由で、小学校6年の時にバドミントンに転向する。水泳で体力がついていた彩子は、生来の負けん気の強さも手伝って、バドミントンの方も驚異的上達。バドミントンでは全国的に強かった私立中学に入学した彩子は、そのまま資質と根性を高く評価され、異例の抜擢で中国遠征に参加したり、全国大会で5位に入賞するという実績も残す。
スポーツでは輝かしい学校生活を送っていたが、順風満帆の思春期とは言えなかったというよりもむしろ、家庭事情の方は実に複雑極まりない「悲惨」きわまりないものだった。
彩子は歳の離れた兄と姉がおり、3人兄弟の末っ子として育てられた。
実は彩子が生まれたとき、彼女の父親は外に愛人を作っていたらしい。もちろん子供の頃の彩子には知るよしもないのだが、中学3年のときに母親からその事実を知らされ愕然とする。「わたしは何のために生まれてきたんだ」という根源的な問いかけがその後の彩子の人生観に大きな影響を残したのは確かだ。「お父さんには外に女がいるんだ」ってグチをいいながら酒をあびるように飲む母親。そんな母親にも「お酒ばかり飲まないでよ」ってどなってばかりいた彩子は、だんだん家庭というものに幻滅を覚えていく。
♪優しい思い出 父さんの背中
欲望はあの人を灰色にした
(ミステリー〜運命〜/『BORO BORO』より)
彩子が中学3年のころから彩子の両親は毎日喧嘩が絶えなかった。父親が勤めていた材木会社は、彩子が小学生の時に倒産し、父親はもう一度会社を作りなおすということで再建したものの、彩子が中学3年の時に再び倒産してしまう。その頃から鈴木家にはお金がなくなり、一気に極貧状態に陥ってしまう。いまどき考えられないことであるが、お米を買うお金すらなかったという状態で、畑をやっていたおばあちゃんからもらった野菜と何とか買ったお米でいつも雑炊を食べていたらしい。学校に穴の開いた靴下をはいていったりというみじめな思いもしている。お祭りに行きたくて家で偶然見つけた200円を、金魚すくいやお菓子に使ってしまったら、実はその200円は鈴木家の1日の生活費で、すごく母親から叱られたとか、彩子が通っていた私立中学・高校の高い学費を彩子の姉が一生懸命バイトして捻出していたというエピソードにはこと欠かない。これは戦後まもなくの頃の話ではない。つい7〜8年前のできごとなのである。
しかし、そんな彩子も今は当時を振り返り、親というよりも、1人の男性、1人の女性として見ることにより、全てを許せるし、母親はどんなにつらかっただろうかと思えると言う。彩子は今、母と姉に一番幸せになって欲しいと願っている。
♪真面目に働いていれば 幸せになれると言われた
息もつけぬ貧しさなら 既に俺はこの目で見た
(BORO BORO/『BORO BORO』より)
そんなむちゃくちゃ悲惨な状態の時にさらに追い打ちをかける事件が降ってわいた。彩子が高校1年の時、父親が自殺未遂をするのである。川辺でお酒を飲んで、石油を車の中に播いて火をつけて死のうとしたという。全身やけどをして病院に運びこまれた。「悪いお父さんでごめんね」という彩子宛ての遺書もあったらしい。
何が何だかわからずにただ泣いているだけだった彩子はただ「お父さんの命が助かってよかった」とだけ思ったという。病院に入院した父親は「せっかく命が助かったんだから、これから死ぬ気で頑張るよ」といった舌の根も乾かぬ3日後には「なんで助けたんだ。俺が死ねば保険金で借金が払えたのに」と母親を責めた。
その後退院した父親は愛人のところに行ったり、家に戻ってきたり、母親とは相変わらず喧嘩ばかりの日々が続いた。
そんな複雑な家庭環境で育った鈴木家の末っ子がグレる環境は、十分すぎるほど揃っていたわけだ。実際に彩子が中学3年の時はちょっと危なかった。たばこを吸って停学処分になる。そのとき彩子は母親に「今度そういうことをしたり、家を飛び出すようなことをしたら、ナイフで首切って死んでやる」と言われて「お母さんに死なれたら困る」と思って自分自身を抑制した。また彩子にはその頃大きな夢があった。もし彼女に夢も目標もなかったら、今頃は人の道を外れていたかもしれない。
♪放課後も 授業中も ひとりきり ただ一度も
好きなように 好きなように 笑えなかったの?
(ひとりぼっちの意味/『19歳の鼓動』より)
その大きな夢のきかっけとなる重大な事件が起こる。現在のアーティスト鈴木彩子は、この事件がなければ存在していなかったであろう。中学3年の秋、クラスの女の子のお供で初めてライブハウスで、あるバンドのライブを見てショックを受ける。ロックやバンドというものにそれほど興味を覚えていなかった彩子の心を、そのライブハウスの大音響がとらえてはなさなかった。そのバンドがやっていた『VOICE』という曲は、彼女の人生観を根底から大きく変えてしまったのである。
♪未来は自分で開け 他人の手を借りようとするな
いつか つかめるはずさ 諦めてちゃ何も見えない
(VOICE〜明日への滑走路〜/『けがれなき大人への道』より)
「そうだ!自分の未来は自分で開かなくちゃ!自分の夢は自分でつかまなきゃいけないんだ。」心も身体も興奮に打ち震えた彩子は、初めて人生においての目標を見つける。
♪こんな家に生まれて来たくはなかった
母の背中に吐き捨てて飛び出した夜
(葛藤/『けがれなき大人への道』より)
高校に人学すると同時に「ロックをやるんなら東京に行くしかないな」という強固な意志を膨らませる彩子。東京に対して凄くひかれるものがあった。
そんなときに「モデルにならないか」と仙台でスカウトされた彩子。モデルをやるということよりも、これをキッカケにして東京に出て行けば、バンド活動、音業活動のチャンスをつかむことができるのではないかと思った。その瞬間、彩子の心はバドミントンや学校への興味を一気に失っていった。
高校くらい卒業しなきゃ親には申し訳ないっていう気持ちはまったくなかった。これだと思い、狙いを定めたら絶対につかみとらなきゃ気がすまない性格だった。でもいろんな人に大反対された。学校では職員会議にかけられ、バドミントン部の先生には殴られたりしたんだけど、それでも毎日「やめさせてください」と土下座して頼んだ。「そんな夢みたいな考えでバンドだ音楽だ、と言っているヤツは社会では通用しないし、そういうヤツらは社会に出る資格は無い!」って毎日のように言われた。そんな長く辛い戦いを経て先生もついに彩子の強固な意志の前に根負けし、とうとうあきらめる。高校を中退し、上京したのだ。
♪おまえらには社会にでる資格がない
冷たい廊下に響いた乾いた声
(葛藤/『けがれなき大人への道』より)
仙台でスカウトされ、モデル業をスタートさせた彩子は、東京・中野の木造モルタル、隣の部屋からの声がつつぬける今にも崩れてしまいそうなアパートでの16歳のひとり暮らしが始まった。ジョンソン&ジョンソン、コカ・コーラをはじめ、いくつかのCMも決まり、そこそこの仕事がスタートしたものの、「何かが違う」と感じはじめたある日、彩子の元に映画主演、レコードデビューという話が舞い込んできた。彩子はそのオーディションにみごと合格。ところが1週間後にクランクインを控えたレコード会社の人とのあいさつの場で「何をやりたいんですか」という問いに「私はロックをやりたいんです。映画やアイドルをやる気はありません」と言ってしまう。集まった関係者は愕然とし、もちろん映画主演、レコードデビューの話はご破算となった。しかし彩子は少しも悲しくなかった。
自分が何のためにバドミントンや学校をやめてまで上京したのかという問いを繰り返した結果「わたしはロックをやりたくて、そのために東京へ来たんだ」という原点に立ち返ることができた彩子。そしていくつかのイザコザを経てモデル事務所をやめて仙台に舞い戻ることになる。
♪まともな人になりなさい 素直な人になりなさい
気がつけばレールの上で 都合よくつくられていた
(BORO BORO/『BORO BORO』より)
とりあえず仙台に戻った彩子は、仙台のイベンター佐藤氏の紹介で代官山ブログクションの新田社長に出会う。新田氏は今まで彩子が会ったことのないタイプの社長だった。今までのモデルとしての実績などは見向きもせずに、開口一番、「ウチの事務所はスパルタだよ。凄く厳しいと思う。それでもついて来れるのか?」という言い方だった。もちろん「ウチの事務所に来てくれ」とも「君が必要だ」って感じではなかった。
意表をつかれた彩子はその瞬間、眠っていた闘争心がムクムクとよみがえり、直観的に「この人は信じられる」と思った。「私は絶対やれます。殴られるのも慣れているし、何があってもついていきます」と答えた彩子。ようやく事務所に入れてもらった彩子に新田氏は「お前の歌も聴いてないし、何をやらせるかわからないぞ」と言ったが、それでもいいと思った。なにか「この人についていけば大丈夫だ」との確信があったと言う。同じく新田氏も直感で”こいつは大丈夫、何かある。”と思ったと言う。
音楽の夢は譲れないという強固な意志を捨ててもいいと思うくらい新田社長(彼女のトータル・プロデューサーでもある)との出会いは、彩子の人生の中で間違いなく第1位の最も衝撃的な出会いだったのだ。
そしてレコードデビュー。デビューシングルはアルフィーの高見沢俊彦氏による『独立戦争』だった。恵まれた楽曲でデビューを飾ったと思えたが、彩子はデビューが早すぎると感じた。ロックっていうのはアマチュアからはい上がってくるものだと思っていたのに、アマチュア経験がまったく無かった彼女にとって『独立戦争』という曲は自分が昔から抱いていた鈴木彩子のロック像と全然かけ離れていると思ったのだ。でもその『独立戦争』は後に「唄を通して何を伝えるべきか」という大切なテーマを考え始めるきっかけを彼女に与えたのである。
初めてステージにたったのは1990年2月1日大宮フリークス。たった4曲しか買わなかったんだけど、身体が宙に浮いているみたいに舞い上がっていた。「私が考えていたライブはこんなんじゃない。しかも『独立戦争』を人前で唄えるほど人間としても大きくない。」って思って悔しくてたまらなかった。それからしばらくライブが大嫌いになる彩子は早くも挫折を味わった。学校はやめたし、モデルもやめたし、家も飛び出してるし、帰るところなんてどこにもない。唄をやめて仙台に帰るくらいなら、死ぬか、どこか行方不明になって体を売ってでも生きるかのどちらかだった。もう崖っぷちの状態で唄い続けるしかなかったのだ。
しかし、そんな後女をいつも励まし、助けてくれたのは、他ならぬ『独立戦争』をはじめとする彼女自身の曲たちだった。
♪神様は何処にいる 未来は誰が創るのか
何を信じて 自由とは…
愛とはいつだって “Let's Stop The War”
(独立戦争/『天地創造』より)
そして、それから1年、またしてもあるひとつの曲との出会いが彼女を変えてゆく。いじめと自殺を題材とした楽曲『ひとりぼっちの意味』にめぐりあったことで、彩子は初めて唄う目的というものを自覚する。この曲の歌詞の元になった、いじめを苦に自殺してしまった女の子のニュースを知っていた彩子は、『独立戦争』にすら押しつぶされそうだった自分がこんなに大切かつ大変な唄を唄っていいのだろうかと大いに悩んだ。そして「この曲にふさわしい人間にならなければ駄目だ。私はきっとそうなろう。」と決心する。
『ひとりぼっちの意味』が、聴いてくれる人を初めて意識した曲だった。人それぞれの使命っていうものがあるとすれば、「私の使命はこれだ」と初めて自覚したと言う。
中学校の時も、モデルの時も、ただただ自己中心で手に入れたいものだけ手にいれてきた。それによってまわりの人が傷つくとか苦労するとか、迷惑がかかるとかを全然考えて無かった。そんな人間が『ひとりぼっちの意味』を唄うというのは、とてつもなく重く大きなものを背負うということになるだろうなと思った。でも他人になんといわれようとも「私の唄うべきものはこういうものなんだ」と確信したのだ。
何かを背負わなければ駄目だと感じること。その葛藤のなかから本当の人間らしさが芽生えてくるし、唄もリアルなものが唄えるようになると思う。つまり鈴木彩子自身の人生そのものを唄に託してみんなに伝えることこそが、鈴木彩子のレーゾンデートル(存在価値)なのではないかと強く感じる。
♪なんにもできなくて
そして終わってく 今日も明日も
消えていった あのこのいのちに
(ひとりぼっちの意味/『19歳の鼓動』より)
このように鈴木彩子の思春期からデビューまでを振りかえってみると、実に波乱に満ちた生き方をしていることがよくわかる。そして彼女の人生のターニングポイント(転機)には、必ず「強固な意志」が介在しているところに注目しなければならない。しかも、その「強固な意志」はまだ人格的にも未熟な、10代の半ばに集中的に現われているのである。家庭内のいろいろなトラブル、学校での反発や衝突、高校中退、映画主演・レコードデビューのキャンセルなど、一人の普通の少女が経験するにはあまりにも多くのことがらを彼女は乗り越えてきている。これらの苦しみ、悩みは彼女に与えられた使命を遂行するための試練だったのかもしれない。この試練を乗り越えてきたからこそ、彼女の楽譜のひとつひとつに圧倒的な説得力とリアリティが満ち溢れているのだ。
この90年代の半ば、自分の力で考えることをせず、自分の力で想像することをしない。あるいは正直とか謙虚さ、思いやりといった人間として当たり前のことに対して「ダサイ!」の一言で唾棄してしまう危ない時代の気分が日本中にはびこっている。鈴本彩子はこの危ない気分を打ち破るべく、この世に舞い降りた傷だらけの天使なのだ。「ほんとのこと」というたったひとつの、しかし他の何ものにも代えがたい「祈り」にも似た見えない翼をはばたかせながら…。
(月刊CLUB 編集出版部 岡本恵ー)